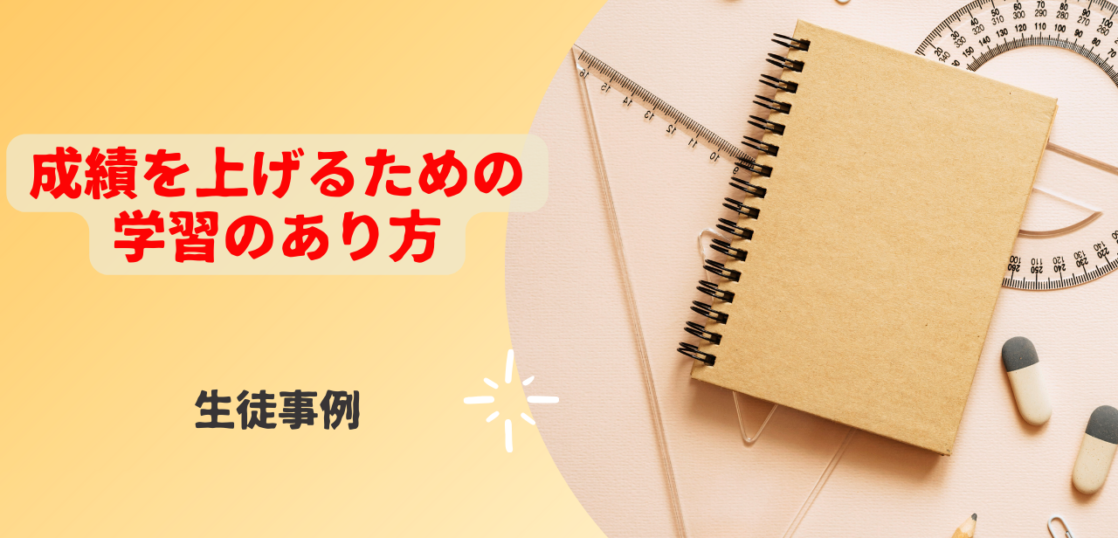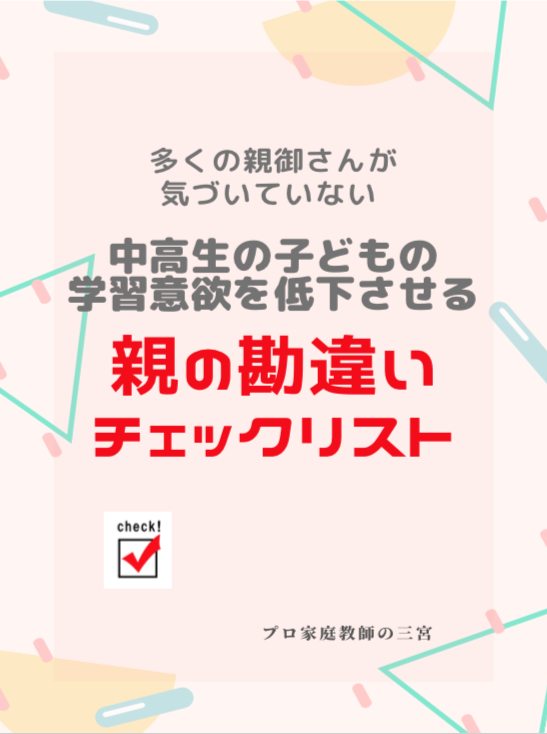目標地点は受験突破のその先、
「自分で自分の人生を切り拓き、自ら幸せになれる力」を身につけ、
「幸せに働ける社会人」になるための、
総合的な教育支援を行っています、
プロ家庭教師/教育コンサルタントの三宮です。
今回は、生徒事例を。
成果を出すために大切なことを、生徒が教えてくれています。
具体的な勉強方法云々ではなく、もっと根底のお話しです。
これを読んでいただくことで、今一度学習環境を見直すきっかけになると思いますので、
ぜひ参考にしてください。
目次
生徒が出した結果
昨年の12月からレッスン開始となった高2のRちゃん。
数学が大の苦手。
大手の予備校に通っているものの、数学が全然伸びない。
ただその時間を過ごしているだけ。
通っていても、できるようになる気がしない。
そんなこんなで
私とご縁がつながりました。
そんなRちゃんでしたが
レッスン開始からわずか2ヶ月、
学年末考査の数学で
2科目とも、過去最高の80点越え!
模試では英語の
偏差値が12もアップ!
という結果でした。
とっても喜んで報告してきてくれました。
さすがの私も、こんなに短期間でこんな成果を
特に英語では点数ではなく、偏差値のほうを12もアップさせてくるなんて
びっくりしました〜。
私がやったことと生徒の変化
一体どんなことをやったんだ?!
と思われるかもしれませんが、
今回私がやったのは
勉強そのものを教えることで成績を上げようとすることではありません。
メンタルトレーニングで
心の状態を良い状態に整えること
レッスンの時間や勉強が「楽しい!」「面白い!」
と感じてもらえるようにすること
です。
メンタルトレーニング中にRちゃんが
「心にアンミカを育てるんですね」
と、面白い表現をしてくれました。
アンミカさん、本当にポジティブで、キラキラ明るい方ですよね〜
上手い表現!!
そうそう、そんな感じ〜〜
数学のレッスン中は
「わ〜、激アツです(なるほど!)」
「なんか、数学が面白いです!」
などと反応してくれていました。
「先生とやったら、数学が楽しいです」
とも言ってくれました。
これ、生徒たちにはちょこちょこ言ってもらえてるんですが
何度言ってもらっても、とっても嬉しいです🎵
さて、Rちゃんはスイッチが入ったのか?
数学は学生泣かせの「数列」をやっていましたが
通常は、
数学が苦手な子は難しくて解くのを避けたり
最終的には「捨てようか」となるような類の応用問題2題、
私も、数学が苦手で普段点数の低い子には
「これは無理に取りに行かなくていいよ〜(他で頑張ろうか)」
と伝えるような問題を
特に熱心に
Rちゃんは自ら何度も何度も繰り返し練習をしていました。
数学の点数を取るための戦略としては
もっと他をやったほうがいいとか色々とありはしますが
数学に苦手意識を持っていたRちゃんが、あえて難しいものに挑戦して
「この問題ができるようになりたい!」と、
「欲」を出してきたことを
私は大きく評価して、応援しました。
他のが手薄になってしまって、直前にあたふたしたりもしましたが、
テストを受けたあと、練習していた2題は
「完璧です!」
と発言。
「本当に数学苦手なん?!」
と疑うほど(笑)、自信満々でしたね。
で、結果的に
数学の2科目とも過去最高得点をとってきました〜。
苦手な数学で難しい問題
自分が熱心に頑張った問題が満点だった
ということが特に嬉しかったようで、
これは確実に、Rちゃんの自信につながっていました。
私も、本当に良い経験をしたなと思います。
英語のほうは、私からのアドバイスをもとにして
Rちゃん自身が選んだものに勉強の仕方を変えました。
(アプリを使った学習)
「私は1日坊主なんです」と言っていたRちゃん。
3日坊主でもないらしい・・笑
その学習方法だったら
「これなら続けられる」「面白い」と言って、
始めてから、なんと1日も休まずに続けていました。
なんと、修学旅行中にもやっていたそうで・・。
これにもびっくり!
「成果が出るのには少し時間がかかると思って、テスト結果にはあんまり拘らずに、楽しんで続けてたらいいからね〜」
と、アドバイスしていたんですが
短期間で、模試の偏差値が12アップしてしまいました。
事例から見る成績アップの鍵
数学過去最高得点!
偏差値12アップ!!
ここに目がいってしまうかと思うんですが
私が注目、評価したいのは、
そこよりも
Rちゃんの中で、勉強に対して
「面白い!」「楽しい!」
という感覚が芽生えていることと
「こうなりたい!」「こうしたい!」
という
「意欲」
が湧いてきたところ。
Rちゃんのお母さんも、
この変化をとても喜んでいらっしゃいました。
「楽しい!」「面白い!」の状態は、
脳は学習することを素直に受け取って、どんどん吸収していきます。
例えば・・・
英単語とか古文の活用形、
イヤイヤやっててなかなか覚えられないのに、
自分の推しの新曲は、あっという間に、
歌詞も応援の仕方も、なんならダンスも覚えてしまう(笑)
これ、ホント、中高生あるあるなんですよ~。
「意欲」のところに関してですが
数学の難問にチャレンジしている、何度もその問題ばかりを練習するということは、そこに時間をかけるわけですから
いかにして全科目のテストの点数を総合的に上げていくか
という点においてはマイナスになりますし
家庭教師としては、本来は矯正するところです。
ですが、私は、テストの点数ではなく
彼女に芽生えてきた「〇〇したい」と気持ちが溢れてきたことや
貴重な経験値のほうを重要視したので、
あえて矯正はしませんでした。
なので私の想定通り、
他の科目が疎かになってしまって、
芳しくない結果になった科目もありました。
ですが、それはたいしたことではないです。
今回のRちゃんの内面の変化、経験が、
今後彼女をさらに大きく伸ばしていきます。
心の状態も成績に大きく影響
メンタルトレーニングの際に
「心にアンミカを育てる」
とRちゃんが表現していましたが
心の状態は、成績が上がっていくために重要な要素です。
本当は結果を出す能力は持っているのに
「出来なかったらどうしよう」という恐れや不安
「自分には無理」という自己肯定感の低さ
そういうことが影響して
結果を出せない状態になっている子たちをこれまでたくさん見てきました。
ですから、
私はメンタルトレーニングを重要視しています。
もともと、
「心が弱い」という自分の状態を変えたいと思っていたRちゃんと
そのRちゃんの状態を認識していたお母さんは
私がやっているこの「メンタルトレーニング」
も、レッスンを受けたいと思われた要因のひとつだったようです。
私としても、
勉強そのものを教えるとか、宿題(勉強)を頑張らせるとか
そんな直接的な方法よりも、
勉強の面白さを伝えたり、メンタルトレーニングをやっていくほうが、
勝手に勉強してくれるようになるし、成績も上がるしで
楽なんですよ。
そして、
自分で心の状態を良好にできるようになる
自分で自分の機嫌を取れるようになることは
社会に出てからも、自分で自分を幸せにしていくことにつながります。
私は、そんな若い子たちを輩出したいと思いながら、
この仕事をやっています。
どんなに勉強ができて、良い高校、大学に進学して、
良いところに就職していっても、年収が良かったとしても
心が不幸だと意味がありませんから。
元々メンタルの改善の余地がある状態のRちゃんは、
今回のテストや模試で、数学や英語を喜びつつも
やはり芳しくなかった科目にかなり囚われているところがありました。
「数学は頑張って結果が良かったけど〇〇が勉強不足で悪かった↓」
という彼女の表現は
「〇〇は勉強不足で悪かったんだけど、苦手な数学であんなに頑張れた!過去一の結果を出せた!自分すご〜い!!(アゲアゲ)」
に、矯正。
こういった、言葉の使い方ひとつひとつを矯正していくことも
自信を持つとか、
内面に変化を起こして結果を出していけるようになることに繋がっていきます。
Rちゃんのお母さんは、
「他の科目の勉強不足は問題ですが、数学が楽しくなっているということが大進歩ですね!」
と表現。
とってもお上手です。
新学年に上がる前に学習環境を見直そう
「しないよりはマシかも・・」
で、高い授業料を払って塾や予備校に通い続けていたり、家庭教師の先生に来てもらっている子は多いですし
中には
「大手だからいいんじゃないか?」
そういう理由で、ダラダラと続けている子もいます。
ハッキリ言って、その状態はおすすめしません。
年度が切り替わるこの機会に
今一度、自分の現状を客観的に見てみて欲しいなと思います。
親御さんだったら、我が子の表情で、現状が良いかそうでないかが分かると思いますし
肝心の本人が
・楽しいとか面白いとか、そういうプラスの感覚が少しでもあって勉強できている状態か?
・「自分できそう」と思える心の状態にあるか?
・その塾、予備校、家庭教師、受けていて本当に役に立っていると言えるか?
・ただ時間だけが過ぎているだけになっていないか?
・受けていることで親を安心させているだけになっていないか?
・本当にこのままで、頑張ろうと思えて、受験を乗り越えていけるのか?
などなど
学生さん本人が、体感として分かるはずです。
中高生にもなれば、自分で冷静に判断できます。
自分の大切な将来に関わることです。
自分のことを人ごとにせずに、よく考えて
あらためて自分の学習環境を整えてください。
良い状態っていうのは、勉強のことだけではないですよ、
心の状態も、いい状態で、ってことです。
「勉強は苦しいもんだ」
は、違いますよ。
この春、学年が切り替わるタイミングは見直しの良い機会です。
このブログには、成績向上のためのヒントをたくさん散りばめました。
1人でも多くの学生さんが
春から良い状態でスタートを切れるようになってくれると嬉しいです。